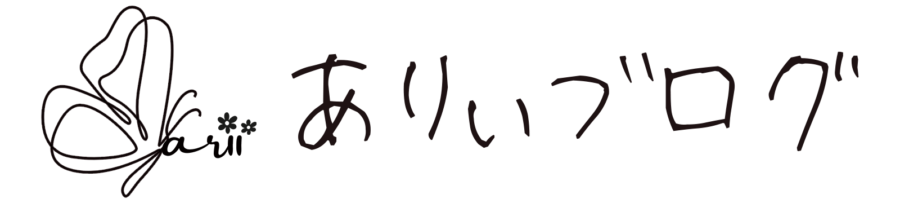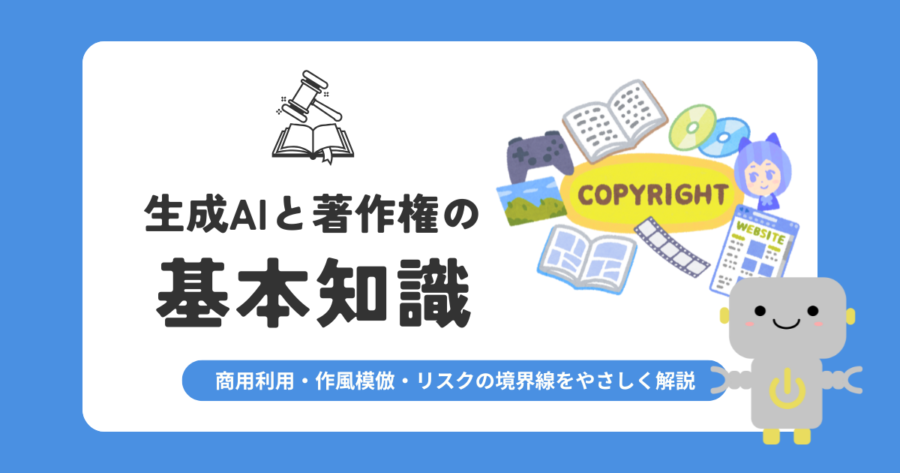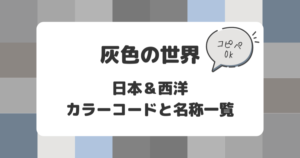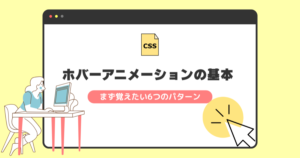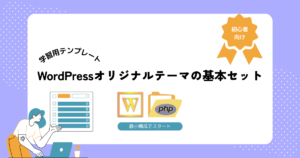商用利用・訴訟リスク・責任の所在をやさしく解説
- AI画像をSNSや商用で使っている
- 作風の“似すぎ”がちょっと心配…
- フリー素材や利用ルール、ちゃんと分かってるか不安
- クライアントに納品しても大丈夫?と迷ってる
- AIをもっと安心して使いたい!
はじめに|生成AIは便利だけど、著作権って大丈夫?
生成AIを活用した画像や文章は日々進化し、商用利用の場面でも見かけることが多くなってきました。
とても便利な一方で、
「著作権はどうなるの?」
「勝手に使って大丈夫?」
と不安に感じたことはありませんか?
実際にあった私の体験
私はデザイナーとして仕事を請け負うなかで、生成AIを活用することもあります。
ところが、納品後にクライアントがその画像を別の媒体で無断使用していたというケースがありました。
当時は納品時の用途に限った使用を想定していたため、意図していない形で使われているのを見て少し戸惑いました。
その際、「これってセーフなの?アウトなの?」と感じたのをよく覚えてます。
この経験から、AI生成画像は特に“使用範囲”を事前に明確に伝えることが大切だと実感するようになりました。
※私はこの画像を自ら生成・加工していますが、生成AIを使った画像は、法的に「著作物」として保護されるかどうかがグレーゾーンとされています。
「著作権がある」と断言はできませんが、OpenAIの規約上は、生成者が使用・商用利用する権利を持つとされており、クライアントへの納品や販促物への活用自体は問題ありません。
ただし、他者による再配布や用途変更の際には、制作側の意図を超えた使用によるトラブル(画質劣化・誤解・拡大印刷時の粗さなど)については、責任を負いかねるケースがあります
AIを使っていて、ふとこんなことを思うことがあります。
- 「AIで作ったイラストをアイキャッチに使ってるけど、これって本当に大丈夫?」
- 「知らずに誰かの作風を真似してたら…訴えられたりしないのかな?」
こういった不安や疑問は、日々AIを使っている中で実際に私が感じているものです。
実際、SNSでは「ジブリ風」のような有名な作風を意識した生成方法を紹介している投稿もよく見かけます。
それを見て、「これって著作権的にどうなんだろう?」と疑問に思うこともありました。
──とはいえ、それを見た他の人がどう感じているかまでは、正直わかりません。
※作風の模倣がどこまで許されるかはケースバイケースですが、「○○風」といった生成画像を商用利用する際には、念のため注意が必要です。
ですがAIの便利さの裏で、何となく不安を抱えたまま使っている人は、意外と多いのでは?とも感じています。
商用でAI画像を使う立場として、「どこまでがセーフで、どこからがアウトか?」という線引きが気になり、今回あらためて情報を整理してみました。
※法律の専門知識があるわけではありませんが、調べたことを初心者の方にもわかりやすくまとめています。
そもそも「著作権」とは?
著作権とは、「創作的な表現をした人に自然に発生する権利」です。
登録などをしなくても、創作した時点で自動的に発生します。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 著作物 | 創作性のある作品(絵・文章・写真など)。誰かの“個性”が入っていることが重要。 |
| 著作者 | その作品を作った人。AIが作った場合、著作者が曖昧になりやすい。 |
| 著作権 | 著作物を無断で使用されないための権利。登録不要。創作と同時に自動発生する。 |
生成AIと著作権:そもそも何が問題?
AIが描いたイラストや、書いた文章。
これは誰のもの? そして、それを使ったら、誰が責任を負うの?
こうした疑問が生まれる背景には、主に2つのポイントがあります。
1. 学習段階の問題
生成AIは、大量の画像や文章など既存の著作物を学習データとして使用しています。
このとき、著作権を持つ作品が含まれている可能性があるため、「学習に使うこと自体がセーフなの?」という疑問が生まれます。
2. 生成段階の問題
AIが出力した画像や文章が、誰かの作品に似ていることがあるという点も、注意すべきポイントです。
特に「○○風(ジブリ風、ディズニー風など)」のような特定の作風を意識した生成物は、著作権や意匠権のグレーゾーンに入ることもあります。
「AIが訴えられる」ことはない。でも…
著作権法の観点では、AIそのものに責任を問うことはできません。
法的責任を問われるのは、AIを使った“人間側”です。
つまり、生成AIを使って何か問題が起きた場合、実際に使用・公開・販売などを行った人に責任が発生するということになります。
- AIの学習元に著作物が含まれている可能性がある
- 出力されたものが他人の作品に似る可能性もある
- 使うのは自由でも、責任は“人間側”にある
だからこそ、商用利用や公開時には「著作権的にどうか?」を使用者自身が意識する必要があるのです。
生成AIが作ったものに著作権はある?
結論から言うと、日本の法律では、AIが自動で生成した画像や文章には著作権は発生しないとされています(2025年5月時点)。
AIは「人間」ではないため、著作権法で保護される“著作物”には該当しないという考え方が基本です。
ただし、人間がどこまで関与したかによって話は変わります。
人がAIに対して工夫したプロンプトを入力したり、生成された画像に編集・合成・装飾などの創作性を加えた場合、その部分については人間の著作物と認められる可能性があります。
| ケース | 著作権扱い | ポイント |
|---|---|---|
| AIが自動で生成した画像や文章 | 著作物ではない(著作権は発生しない) | 人間の創作性が関与していないため |
| 人が工夫してプロンプトを入力・編集 | 内容によっては著作権が認められる(創作性があれば可能性あり) | 具体性・表現意図が鍵になる |
| 複数画像を合成・装飾したAI画像 | 編集者の著作物とされる可能性あり(構図・表現が鍵) | レイアウト・構図・加工の創作性が重要 |
生成AIの画像や文章を「そのまま納品・公開」する場合は、著作権を主張できない前提で取り扱うのが無難です。
商用利用時には「誰が責任を持つのか」「第三者が自由に再利用しても問題ないか」をよく確認し、納品物にする場合は加工の有無や制作フローを明確にしておくことが重要です。
AIで著作権侵害になるケースとは?
AIを使って生成したコンテンツでも、以下のような場合は著作権侵害に該当する可能性があります。
- 有名キャラクターや漫画の絵柄に酷似した画像をAIで生成・公開した場合
- 誰かの絵柄や作風をそっくり真似た画像を商用目的で使用した場合
- AIに文章を生成させた結果、他人のブログや記事と酷似した内容になっていた場合
これらのケースでは、以下の2つの要素が揃うと著作権侵害と認定されるリスクがあります。と、著作権侵害と認定されるリスクがあります。
▸ 依拠性(いきょせい)
→ 元の作品を参考にしている、または影響を受けていること
(例:AIの学習データに元作品が含まれていた、模倣する意図があった など)
▸ 類似性(るいじせい)
→ 見た目や構成・文体・表現が似ていること
(完全コピーでなくても、“似ている”と判断される可能性があります)
著作権侵害は「そっくりかどうか」だけでなく、
「元作品に依拠しているかどうか」も重要な判断基準になります。
AIが自動で生成したものであっても、
結果として他人の作品と似てしまった場合は、利用者側が責任を問われる可能性があることに注意しましょう。
商用利用で気をつけたいポイント
| ケース | 判断基準 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自分で生成したAI画像を使う | 基本OK | 他人の作風に似すぎていないか要チェック |
| 有名人そっくりの顔を生成 | グレーゾーン | パブリシティ権(肖像権)を侵害する恐れあり |
| 「ジブリ風」「◯◯風」などの作風模倣 | 要注意 | 特徴的すぎると訴訟対象になるリスクあり。特に明確な構図の模倣は危険 |
| フリー素材サイトのAI画像を使う | 条件次第 | 商用利用OKか、クレジット表記の有無など利用規約を必ず確認 |
実際にあった著作権トラブルと各国の法的スタンス
生成AIと著作権をめぐる問題は、国や地域によって対応が異なります。
また、実際に起きた訴訟やトラブルの事例からも、注意点が見えてきます。
【1】国別スタンスまとめ|各国での違いをざっくり把握
| 国・地域 | 学習データ利用 | AI生成物の著作権 | プラットフォーム責任 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 比較的寛容(著作権法30条の4) | 原則なし(人間関与が前提) | 削除対応しないと責任問われることも |
| 米国 | フェアユース理論 | AI単独の創作物はNG | Section 230により一部免責(例外あり) |
| EU | オプトアウト可能 | 原則NG(人間の創作のみ保護) | DSAにより責任強化中 |
| 中国 | 厳格に管理 | 人間の関与があればOKになることも | 合成コンテンツに表示義務あり |
なお、AIと著作権に関する議論は今後も進んでいくと予想され、各国で法整備の動きも活発化しています。今後の動向にも注目しておくと安心です。
【2】名誉毀損・プライバシー侵害にも注意
AIが実在人物や虚偽の情報を出力するケースもあります。
これにより以下のようなリスクがあります:
- ChatGPTが「○○市長は贈収賄で服役」と出力 → 名誉毀損問題に発展
- 顔写真からポルノ画像を自動生成 → ディープフェイク問題(肖像権・プライバシー)
このようなケースでは、生成元に悪意がなくても、“使った人”が責任を問われるのが原則です。
【3】実際の事例から学ぶ|国内外の著作権トラブル
| 事例名 | 内容 |
|---|---|
| イラストACでのAI画像削除 | 作風が既存作品と酷似しているとして、AI画像が削除された事例 |
| Midjourneyの訴訟(米国) | 著名作家の画風に酷似したAI画像で訴訟。元画像が明確だったため「依拠性」ありと判断 |
| Stable Diffusionの集団訴訟 | 「誘発的著作権侵害」としてAI開発側が訴えられる |
| 中国:ウルトラマン風AI画像 | キャラクター風画像が著作権侵害と判断され削除対象に |
| 日本:文化庁の見解(2024年) | 「AIでも依拠していれば著作権侵害になる」と明言 |
【4】私自身の経験から(リアルな補強)
これまでにも触れてきた通り、生成AIの出力物そのものには著作権が発生しません。
ただし、自分で構成や合成など独自の加工を加えた部分には著作物としての保護が認められる可能性があります。
実際に、私も以下のような経験がありました。
生成AIで作成・加工した画像を納品後、別媒体で無断使用されていた
このケースを整理すると:
| 要素 | 判断 |
|---|---|
| 自動生成された部分 | 著作権なし(原則) |
| 加工・構成した部分 | 創作性があれば著作権が発生する可能性あり |
とはいえ、AI画像まわりはまだグレーな部分も多く、“どこまでが自分の権利になるか”は曖昧になりやすいと感じています。
納品前に「使用範囲」や「再利用可否」を明確にしておくことが、後々のトラブル防止につながります。
制作者・クリエイターが意識すべき5つのポイント
- AIで制作したことは、可能であればクライアントに伝える(※明記推奨)
→ 特に商用利用の場合、責任の所在を明確にしておくことが重要です。 - フリー素材の利用ルールを厳守する
→ 「商用OK」「再加工OK」など、各サイトの利用規約を必ず確認しましょう。 - 他人の特徴的な作風は避ける
→ 似た絵柄・世界観になりすぎないよう、構図や加筆で“自分の創作性”を加える工夫を。 - 人物を扱う場合は、肖像権・モデル規約にも注意
→ 実在の人物に似た画像や、モデル素材の使用には使用範囲の確認が必須です。 - プロンプトや構成・仕上げを通じて“著作性”が生まれることも
→ 完全自動生成よりも、人の判断が加わることで著作物と認められる可能性が高まります。
よくあるグレーゾーンと注意点
- スタイルの模倣はOK?
-
文体や絵柄などの「作風」は、著作権の対象ではないことが多いですが、
あまりに酷似していると、不正競争防止法やパブリシティ権の侵害に問われるリスクがあります。 - プロンプトに頼っても著作権は得られる?
-
単にAIが出力したものを使うだけでは著作権は発生しません。
ただし、人間の創作性(選定・調整・加工・構成など)が加わっていれば、
著作物として保護される可能性もあります。
まとめ|AI時代の創作は“知らないと損する”
生成AIはとても便利なツールですが、著作権や肖像権に関する基本的な理解がないまま使うと、思わぬトラブルにつながることもあります。
法律が追いついていないグレーゾーンも多いため、「知らなかった」では済まされないケースがあることも事実です。
制作物を届ける側として、発信する立場として、
最低限のリテラシーを持ちながら、安心してAIを活用していきたいですね。
- 生成AIと著作権の基本的な考え方
- 商用利用時に注意すべきポイントと回避策
- 実際のトラブル事例とリアルな視点(筆者の体験含む)
- AIを使っても、責任は“使った人”にあるという前提
- 著作権侵害・名誉毀損リスクはゼロではない
- 商用利用OK」と書いてあっても、正確な理解が大切
- 趣味でも商用でも、「どこからがNGか」を知っておくことが安心につながる
AIを使うこと自体がリスクではありません。
「どう使うか」を判断できる知識が、これからのクリエイターには必要だと思います。
※本記事は法律の専門的なアドバイスを提供するものではありません。
最新の法改正や事例については、専門家や各種ガイドラインをご確認ください。